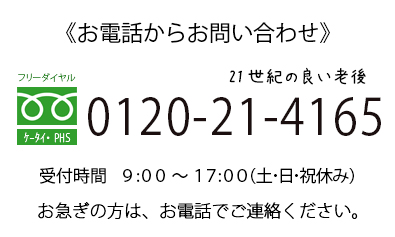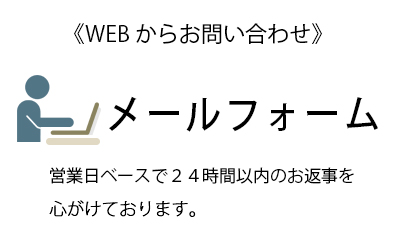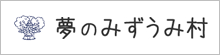今年も11題がエントリーされました。
テーマは
○生きがい東雁来:「日曜日デイの取り組み ~苦悩と喜び、そして得たもの~」
○うらら伏古: 「Mさんの認知症状とDT効果の相関」
○F委員会:「凍結含浸法に挑戦」
○せんり: 「長寿館の人々と少しずつDT」
○てんや本町:「(仮)よーし!!打合せするぞ ~本町の第2の職員~」
○えくぼ元町: 『蓮川先生に学ぶ「日本の心」「和の心」(仮称)』
○第3事業部:「DTの取り組み」
○第2事業部: 『SONASセッション後のDT実践 「笑顔がみたい」 』
○第4・5事業部: 「乙女のつどい」
○てんやわんや: 「絶対行きたいてんやわんや~男性利用者さんの活動~」(仮)
○えくぼ:「DTへの取り組みinかまくら(仮)」
今年も各事業所・事業部が素晴らしい発表をしてくれることと思います
開催後、取り組み事例や最優秀賞などの報告を楽しみにしていてください。